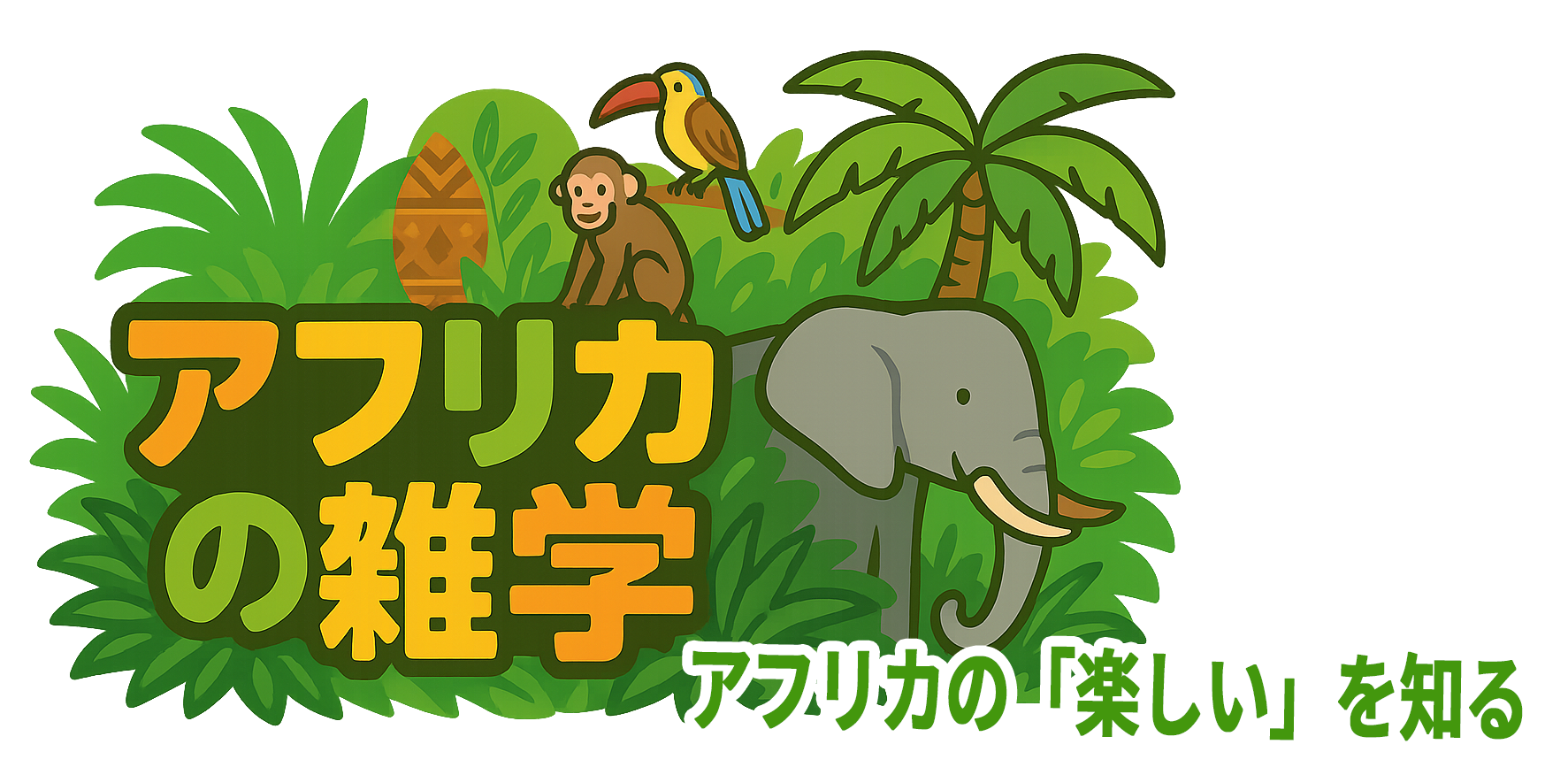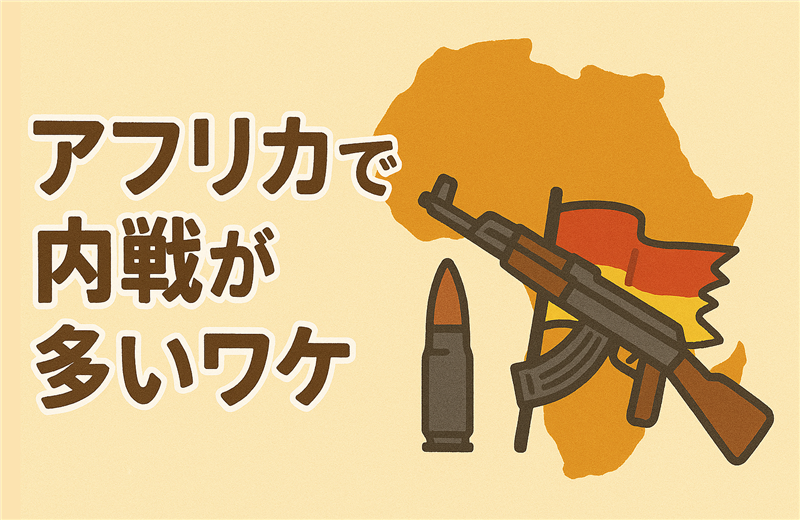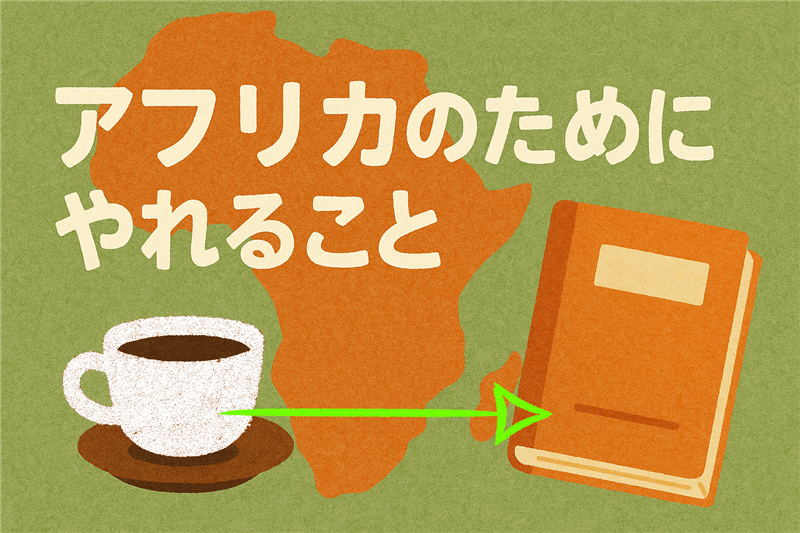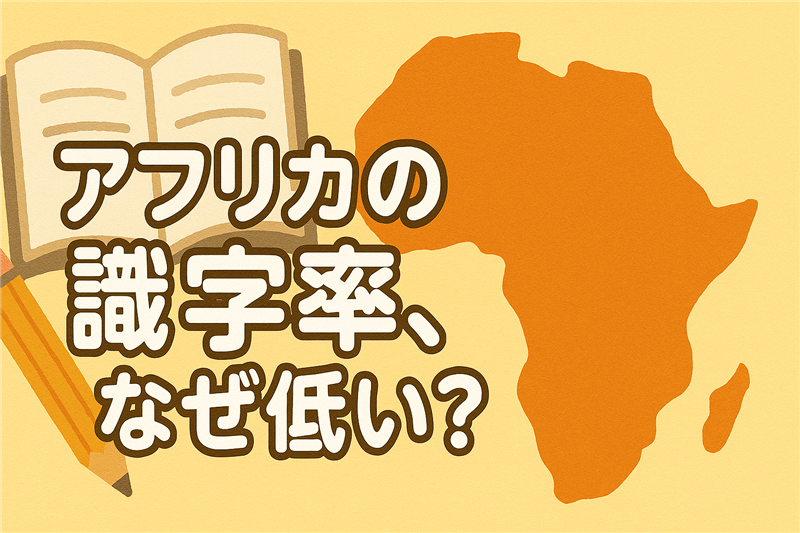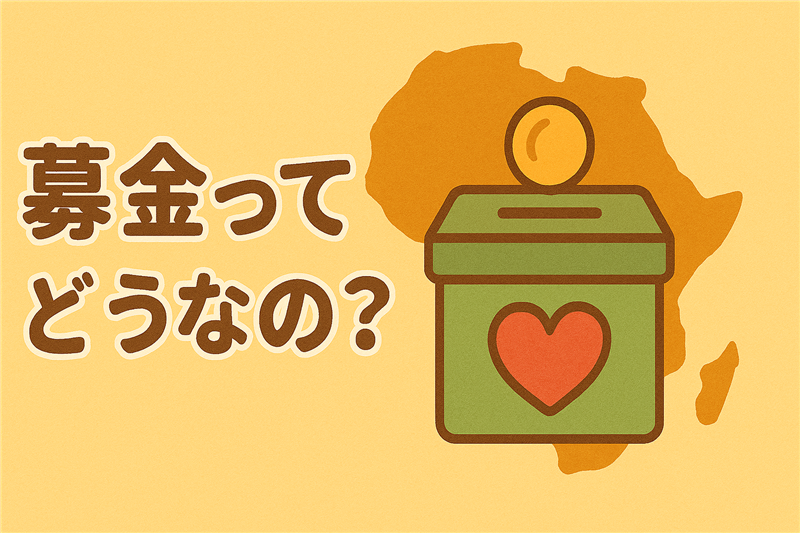アフリカ情勢でよく聞く「無政府状態」とは?どうなることなの?
「無政府状態(むせいふじょうたい)」って、なんだか物騒な言葉に聞こえますよね。ニュースで「アフリカの○○国は今、無政府状態に陥っています」なんて報じられると、
「政府がないってどういうこと?」
「そんな状態で国が回るの?」
って思っちゃうかもしれません。
でも、この“無政府状態”っていうのは、ただ政府の建物がなくなるとか、誰も大統領じゃないとか、そういう表面的な話じゃないんです。
ここでは、アフリカ情勢でしばしば問題になる「無政府状態」って何か、それが起きると社会がどうなるのかを、やさしく解説していきます!
|
|
|
「無政府状態」ってどういう意味?

モガディシュのグリーンラインの無人の通り(1993年)
対立勢力の前線となった都市の分断線に人影がなく、統治の空白が生んだ無政府状態の実情を示す。
出典:『An abandoned MOGADISHU Street known as the Green Line, Jan 1993』-Photo by PH1 R. ORIEZ/Wikimedia Commons Public domainより
無政府状態とは、かんたんに言えば── 国の政府や行政の仕組みが機能していない状態のこと。
もうちょっと具体的に言うと:
- 法律が守られない
- 警察や裁判所が動いていない
- 大統領や議会がいても国民を統治できていない
- 複数の武装勢力が勝手に支配している
つまり、「政府が存在しているか」よりも“機能しているかどうか”が重要なんですね。
どんな国が“無政府状態”になるの?
アフリカのいくつかの国では、長い歴史の中で内戦・クーデター・外国の介入といった深刻な出来事がたびたび起こってきました。これらの要因が重なると、国家としての統治機能が大きく損なわれ、人々の暮らしが著しく不安定になることがあります。
その結果、中央政府の力が弱まり、一時的、または長期的に「無政府状態」と呼ばれる状況に陥った国も存在します。以下に、代表的な例をいくつか紹介します。
ソマリア
1991年に当時の政権が崩壊して以降、長い間にわたって中央政府が機能しない状況が続きました。首都モガディシュ以外の地域では、各地の軍閥やイスラム過激派などが勢力を拡大し、国全体がバラバラに統治されていたのです。国際社会の支援を受けて暫定政府が設立されても、安定には程遠い時期が長く続きました。
リビア
2011年、長年独裁体制を維持してきたカダフィ大佐が反政府勢力によって打倒されましたが、その後は新たな権力の空白が生まれ、国内が混乱します。西と東で異なる政府が成立し、「一つの国に二つの政府がある」といった異常事態が長く続きました。各地で武装勢力が独自に支配する地域も多く、現在でも完全な安定には至っていません。
中央アフリカ共和国
この国では、政権の奪い合いや宗教を背景とした対立が続いてきました。クーデターの発生やイスラム系・キリスト教系民兵の衝突によって、首都バンギを除く多くの地域で中央政府の支配力が及ばない状況となり、人々が武装集団の統治下で暮らさざるを得ないこともあります。
どの国にも共通しているのは、政治の崩壊と、それに乗じた武力勢力による支配が入り混じっているという点です。国家としての制度が弱まると、混乱の中で力を持つのは「話し合い」ではなく「武器」になってしまうのです。
|
|
|
無政府状態になると、何が起こるの?

ソマリア沖の海賊容疑者が乗る小型ボート
航路の安全が脅かされると取引と補給が滞り、無政府状態と結びついた沿岸で治安悪化が進みやすくなる状況を示す。
出典:『Suspected pirate skiff near Somalia』-Photo by U.S. Navy/Wikimedia Commons Public domainより
一言でいえば、「社会が“自己責任”になる」状態です。つまり──
- 法律に守られない → 強盗や暴力が横行
- 医療や教育が受けられない → 社会サービスの崩壊
- 避難民が増える → 国外に逃げ出す人も多数
- 食料や物資が届かない → 人道危機に発展
- テロ組織や海賊が出現 → 世界的な治安問題に
たとえば、無政府状態だったソマリアでは、武装グループが“私設税金”を取る、海賊が外国の船を襲うなど、まさに「国家が機能しない」とこうなる、という典型例が見られました。
なぜ簡単に立て直せないの?
「じゃあ新しい政府をつくればいいじゃん」と思うかもしれませんが、 無政府状態に陥った国では、信頼や秩序が根こそぎ崩れているため、簡単に立て直せないんです。
その理由は:
- 複数の勢力が権力をめぐって対立している
- 国民の多くが政府そのものを信用していない
- 外国の介入が混乱を深めていることもある
- そもそも“国としての仕組み”が未整備
そのため、再建には安全保障、政治合意、人道支援、教育、インフラ整備といった、 あらゆる分野の「一からの再構築」が必要になるんですね。
でも、希望もある

モガディシュのピースガーデン(ハマル・ジャジャブ地区)
内戦で荒廃した公共空間を再整備し、市民の憩いの場として機能を取り戻した様子を示す。帰還したディアスポラの投資や外交拠点の再開など、復興の動きが街並みに反映されている。
出典:『2015 12 New face of Mogadishu-20』-Photo by AMISOM Public Information/Wikimedia Commons Public domain
どんなに深い混乱に陥ってしまったとしても、そこから立ち直った国も、ちゃんと存在します。無政府状態になった国々でも、人々が平和を願い、努力を重ねることで、少しずつ社会の秩序や政府の機能を取り戻していったんです。
ソマリアの例
長らく混乱が続いていたソマリアでも、2012年に国際的な支援を受けて新たな連邦政府が誕生しました。この動きは、国内の対話や和解を後押しする大きな一歩となりました。特に首都モガディシュでは、少しずつですが治安が改善され、学校や病院といった公共サービスも再び動き出しています。まだ課題は多いですが、確かな回復の兆しが見えてきているのです。
リベリアの例
西アフリカのリベリアでは、1989年から続いた凄惨な内戦が2003年についに終結。平和への道のりは決して平坦ではありませんでしたが、国連の平和維持活動や支援が大きな助けとなりました。そして何より象徴的だったのは、2006年にアフリカ初の女性大統領としてエレン・サーリーフ氏が誕生したこと。彼女のリーダーシップのもとで、国民が一致団結して復興を進め、リベリアは再び歩みを取り戻しました。
対話・和解・国際協力──これらがあれば、たとえ一度すべてを失ったとしても、「もう一度国家をつくり直す」ことはできるんです。過去に混乱を経験した国々の再生の歩みは、今まさに困難にある地域にとって、大きな希望の光になります。
アフリカで起きる「無政府状態」は、単なる政治の混乱ではなく、人々の命や暮らしそのものが揺らぐ非常事態です。でもそれは同時に、「どうやって国家を築き直すか」「社会の信頼をどう取り戻すか」という問いでもあります。混乱の中でも、再出発に挑む声があることを、忘れないでいたいですね。
|
|
|