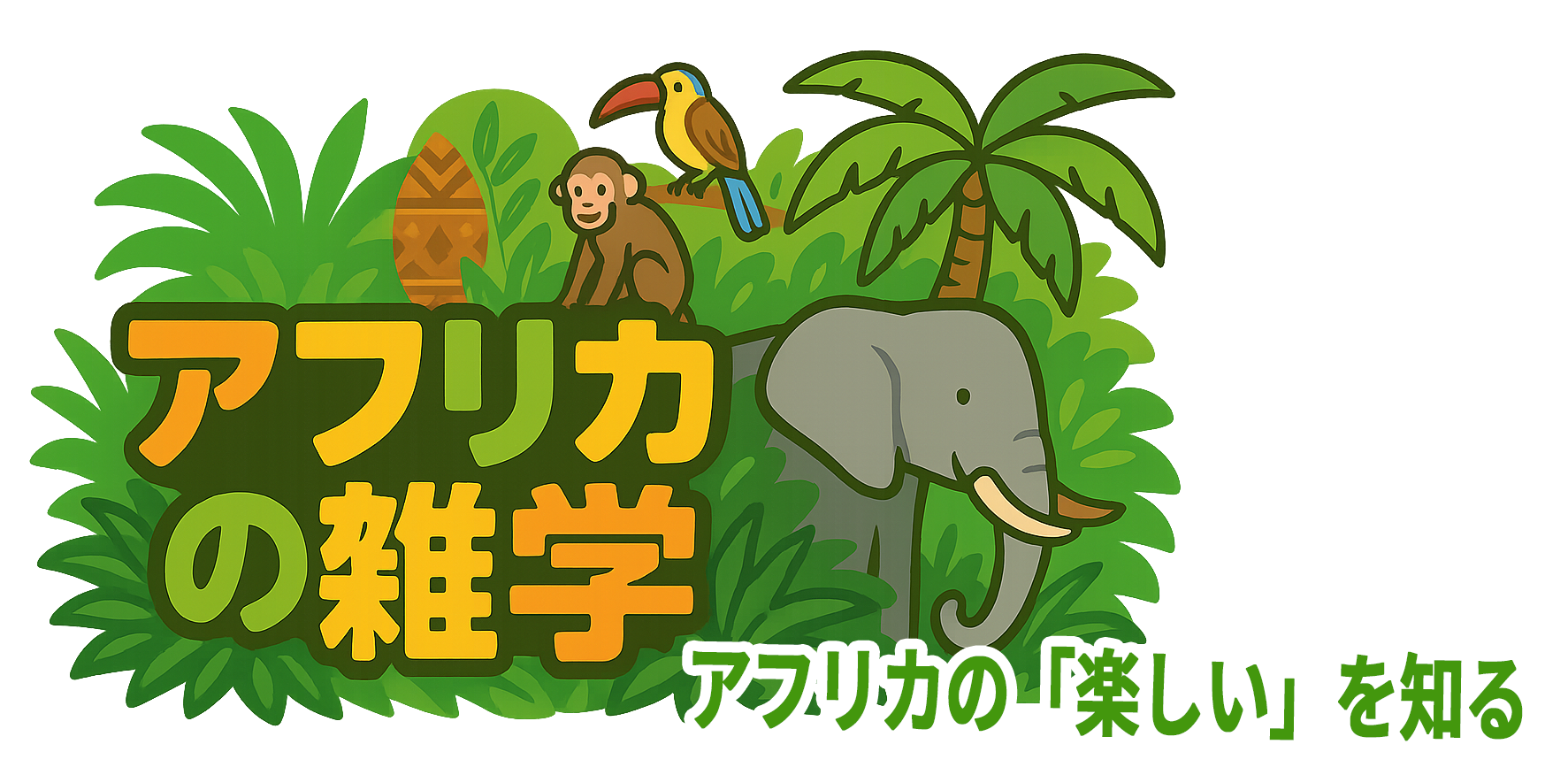アフリカにおけるカカオ栽培の歴史
チョコレートの原料としておなじみのカカオ。
実はその7割以上がアフリカで栽培されているって知ってましたか? とくに西アフリカ──コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアなどは、まさに“世界のカカオ畑”なんです。
でも、カカオってもともと南米原産。じゃあ、どうやってアフリカにやって来たの?そして、なぜここまで巨大な産業になったの?という疑問が浮かびますよね。
この記事では、そんなアフリカにおけるカカオ栽培の歴史をたどりながら、その背景にある人々の暮らし、経済、そして世界とのつながりを見ていきましょう!
カカオは“外から来た”作物だった

カカオの原産地は、アマゾン川流域を中心とした中南米の熱帯地域。古代マヤやアステカでは神聖な飲み物とされ、カカオ豆は貨幣としても使われていたほど。
それが15〜16世紀、スペインやポルトガルの植民地支配を通じてヨーロッパに持ち込まれ、“甘い飲み物”としてのカカオ文化が始まりました。
そして19世紀以降、ヨーロッパの需要が急拡大するとともに、植民地の熱帯地域にカカオの栽培が広がっていったんです。その移植先のひとつが、アフリカだったというわけですね。
最初のカカオ畑は“ガーナのとなり”から
アフリカで最初にカカオが栽培されたのは、今の赤道ギニアやサントメ・プリンシペといった赤道付近の島国。ポルトガル人が19世紀前半に持ち込み、プランテーションで栽培が始まりました。
その後、1880年代頃にガーナ(当時は英領ゴールドコースト)にカカオが入ってきたことで、大きな転機を迎えます。
このとき、カカオをガーナに初めて持ち込んだのがチフォ・ドム(Tetteh Quarshie)という人物。彼はフェルナンド・ポー(現・赤道ギニア)から苗を持ち帰り、自分の農地で育て始めたんです。
ここから西アフリカ一帯へのカカオ拡大がスタートしました。
植民地支配と“カカオ経済”の始まり

ガーナ・ブンソ農園でのカカオ豆の乾燥検査(1957年)
英領ゴールドコースト期に農業官吏が天日乾燥中のカカオ豆を検査している場面で、ガーナのカカオ栽培史を物語る記録写真。
出典:『The National Archives UK - CO 1069-46-5』-Photo by The National Archives UK/Wikimedia Commons OGL v1.0
ガーナやコートジボワールなどでは、カカオが換金作物=キャッシュクロップとして急成長。20世紀初頭からは、イギリスやフランスの植民地政府がカカオ生産を奨励し、輸出用のモノカルチャー経済が形成されていきました。
ただしこの構造、表面上は「農民が自由に栽培している」ように見えても、実際は価格・輸出ルート・市場のすべてを宗主国が管理していたというのが現実。
農民にとっては価格が安定しない・利益が薄いという厳しい状況が長く続いていました。それでも、土地の小規模農民たちはカカオによって学校に行かせたり、家を建てたりと、少しずつ生活の基盤を築いていったのです。
|
|
|
“独立後”も変わらない依存構造

ガーナのカカオ豆の天日乾燥
カカオ輸出は、ガーナの経済を支える柱であると同時に、モノカルチャー経済の典型的な事例
出典:『Cocoa beans on a dryer』-Photo by MayorParis/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
1960年代以降、アフリカ諸国が独立を果たしても、カカオ依存の経済構造はあまり変わりませんでした。
とくにコートジボワールとガーナは、現在でも世界のカカオ生産の半分以上を占めていて、まさに“チョコレートの源”なんです。
でも問題は、ここまで作ってるのに──
- チョコレートを作って輸出しているわけではない
- カカオ価格の決定権は国際市場にある
- 児童労働や森林伐採の問題が深刻
という点。つまり、原料はアフリカ、生産はヨーロッパやアジアという“グローバルな分業構造”がずっと続いてきたんですね。
今、カカオに“変化の風”が吹いている
そんな中、近年ではガーナやコートジボワールを中心に、カカオ価格の交渉力を高めようとする動きが出てきています。
たとえば──
- 「リビング・インカム差額(LID)」という上乗せ価格の導入
- 現地での加工・チョコレート製造の促進
- 児童労働の根絶に向けた国際的パートナーシップ
また、ルワンダやタンザニアなどの新興カカオ産地では、クラフトチョコレートとして輸出される動きも。
「アフリカから高品質なカカオを、フェアに世界へ」という新しいストーリーが、少しずつ始まっています。
アフリカのカカオ栽培の歴史は、単なる農業の話ではなく、植民地支配・貧困・世界経済との関係など、たくさんのテーマがつながっています。でもその一方で、そこから新しい道を切り拓こうとする動きも確かにある。カカオには、苦味と希望が、どちらも詰まっているんですね。
|
|
|