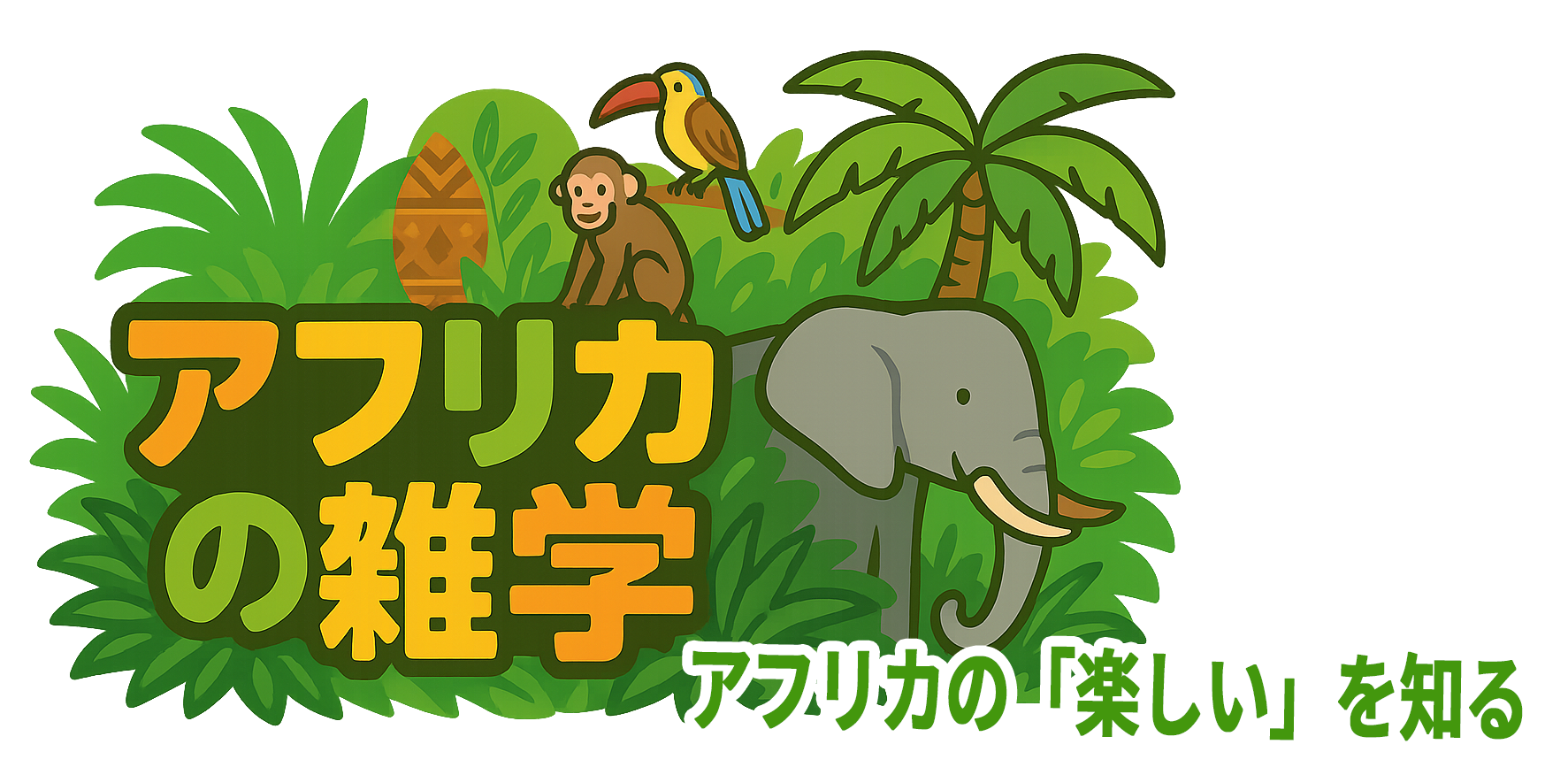アフリカ文学の特徴を歴代の名作を例に解説!
アフリカ文学って聞くと、ちょっとむずかしそう…って思うかもしれません。でも実は、アフリカの物語ってすごく“語りかけるような力”があるんです。
それもそのはず。アフリカにはもともと「口承=語りの文化」が根づいていて、昔から物語は“読まれる”より“語られる”ものだったんですね。
それが文字文化と出会って、小説や詩になったときに、独特のリズムや臨場感が生まれたんです。
ここでは、そんなアフリカ文学の特徴を、歴代の名作・名作家たちを通して紹介していきます!
|
|
|
植民地体験と「自分たちの声」の再発見

チヌア・アチェベ(1930 - 2013)
『崩れゆく絆(Things Fall Apart)』で知られるナイジェリアの作家。講演で語る表情から、アフリカ文学を切り開いた存在感が伝わる。
出典:『Chinua Achebe (cropped)』-Photo by Stuart C. Shapiro/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より
アフリカ文学の大きなテーマのひとつが、植民地支配の記憶です。
欧米によって言語や文化を奪われ、アイデンティティを問われた中で、「自分たちの言葉で、自分たちの物語を語りたい」という強い願いが作品に表れているんです。
その代表が、ナイジェリアの作家チヌア・アチェベの『崩れゆく絆(Things Fall Apart)』。
これは、イギリスの支配が迫る中で揺れ動くイボ族の社会と、一人の戦士オコンコウォの生きざまを描いた物語。
西洋から見たアフリカじゃなく、アフリカ自身の視点から描かれた最初の大作として、今も世界中で読まれ続けています。
口承とリズムが生きる“語りの文学”

ニジェール・ディファのグリオ
弦楽器を奏し語りを紡ぐ職能民で、歴史や系譜、物語を口承で伝えてきた存在。グリオの語りは書かれた文学の土壌にもなり、アフリカ文学の源流を体現する。
出典:『Diffa Niger Griot DSC』-Photo by Roland/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0より
アフリカ文学の特徴のひとつが、リズムのある文章やくり返し表現の多さ。 これは、昔ながらのグリオ(語り部)文化の影響なんです。
耳で聞いて覚える物語には、リズムや抑揚が必要だから、アフリカの作家たちはそれを文章の中にも自然に取り込んでいます。
たとえばセネガルの作家ウスマン・センベーヌの『神の木の下で』や、マリのアマドゥ・ハンパテ・バーの作品では、詩のような語りが繰り返されていて、読むと自然とリズムを感じるんです。
つまり、“読む”というより“聞こえてくる”小説なんですね。
|
|
|
女性たちの声が文学を変えていく

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ(1977 - )
『アメリカーナ』やTED講演で知られるナイジェリア出身の作家。朗読と語りで物語の力と社会への眼差しを伝える。
出典:『Chimamanda Ngozi Adichie』-Photo by Sizzlipedia/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より
近年のアフリカ文学では、女性作家の活躍がすごく目立ってきています。 その中心人物のひとりが、ナイジェリアのチママンダ・ンゴズィ・アディーチェ。
代表作『アメリカーナ』では、ナイジェリアからアメリカへ渡った女性の視点から、アイデンティティ・差別・恋愛をリアルに描いていて、世界中で大ヒットしました。
彼女の作品は、「フェミニズムとは何か」「語ることの意味は何か」という問いかけがこめられていて、アフリカ文学の新しい可能性を切り拓いています。
現代のリアルを描く、都市と移民の物語
現代のアフリカ文学では、伝統や村社会だけじゃなく、都市の暮らし、移民としての葛藤を描いた作品もどんどん増えています。
南アフリカのジョン・クッツェーは『恥辱』で、アパルトヘイト後の社会に生きる人々の孤独や暴力を鋭く描き、ノーベル文学賞も受賞しました。
また、ケニア出身のングギ・ワ・ティオンゴは、かつては英語で作品を書いていましたが、途中から自分の母語であるキクユ語で書くことを決意。これは言葉そのものが文化と権利の問題だという強いメッセージなんです。
“アフリカ”ではなく“アフリカたち”の文学

トンブクトゥ写本の保存作業
西アフリカの学術都市トンブクトゥに伝わる写本群は、法学・歴史・詩・天文学など多様な知の記録で、アフリカ文学の歴史を物語る象徴的資料。現地では修復やクリーニング、デジタル化が進められている。
出典:『Timbuktu Manuscript』-Photo by Mark Fischer/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0より
最後に大事なのは、「アフリカ文学」とひとくくりにすること自体が、ある意味ちょっと危ういってこと。
なぜなら、アフリカには何百という言語、文化、歴史、視点があるから。同じアフリカでも、エチオピアとセネガル、南アフリカとコンゴでは、背景も表現もまったく違います。
だからこそ、アフリカ文学とは“ひとつの声”じゃなく、“たくさんの声が交差する場所”。その多様性こそが、アフリカ文学のいちばんの魅力なのかもしれません。
アフリカ文学は、過去の記憶と今の暮らし、個人の声と共同体の物語、口承のリズムと文字の力がぜんぶ溶け合った、“生きたことば”の集まりなんです。読むたびに、新しい世界とのつながりが見えてくる──そんな奥行きのある文学なんですね。
|
|
|