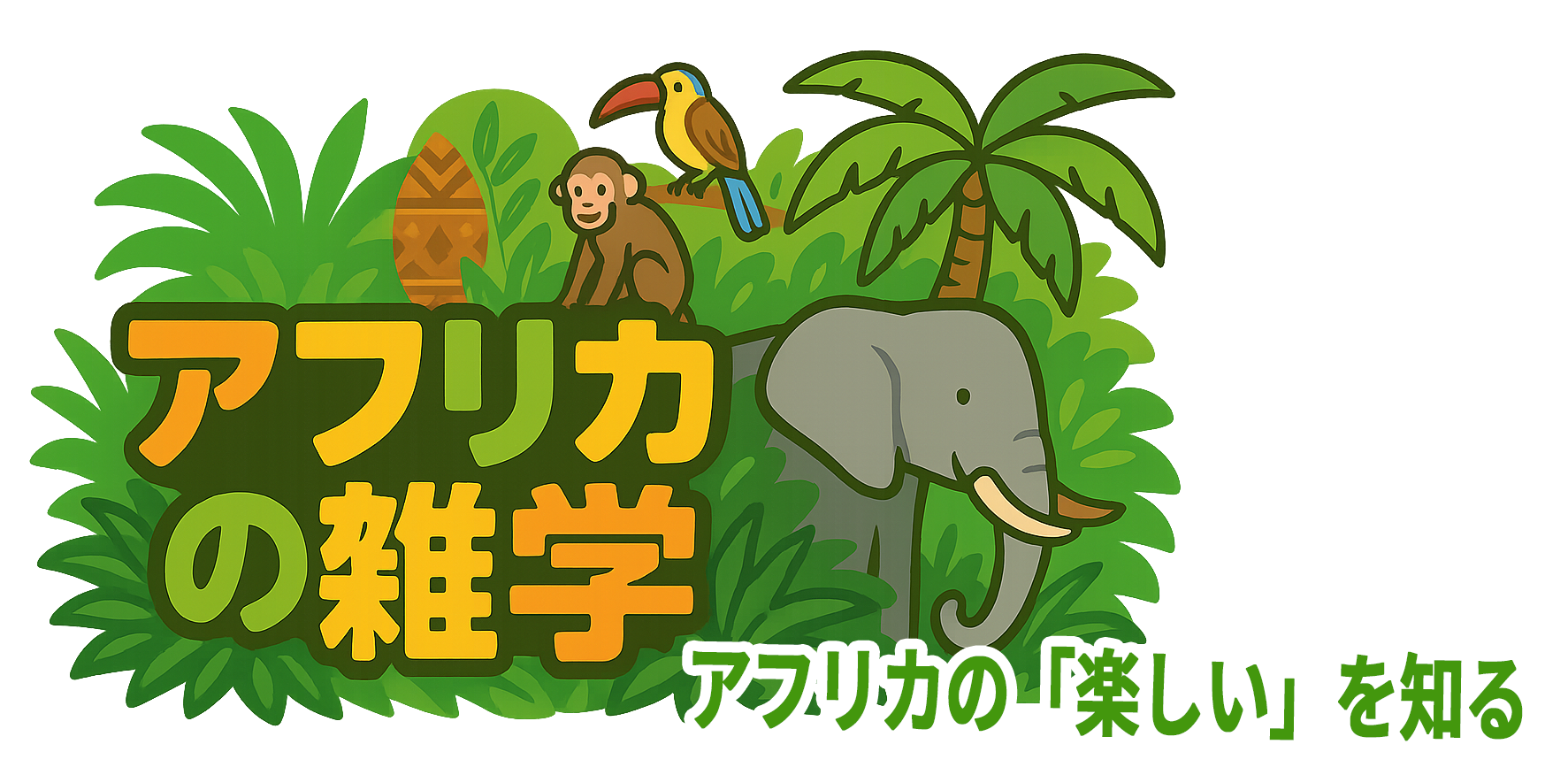アフリカにも“妖怪”はいる?現地の精霊・怪物・民間伝承まとめ!
「妖怪」って聞くと、日本のぬらりひょんや河童、ヨーロッパなら吸血鬼や人狼を思い浮かべますよね。でも、実はアフリカにも“妖怪っぽい存在”がしっかりいるんです。もちろん「妖怪」という言葉は使わないけれど、精霊、怪物、呪霊、変身する動物といった存在が、各地の民間伝承の中で生き続けています。ここではそんなアフリカの不思議な存在たちを、地域別にわかりやすく紹介していきます!
|
|
|
アフリカの“妖怪”=精霊・霊獣・変化する存在たち
アフリカでは「妖怪」というよりも、精霊(スピリット)や呪霊、獣に姿を変える者などとして語られることが多いです。その多くが、自然との関係や祖先信仰と深く結びついていて、「悪いことをすると出てくる」とか「特定の場所に行くと現れる」といったストーリーで伝えられています。
しかもこれらの存在は、ただの“怖い話”ではなく、道徳やタブーを教える教育的な役割もあったりするんですよ。
西アフリカ:呪術と変身の世界
トコロシュ
トコロシュ(Tokoloshe)は、南部アフリカに伝わる、背が低くて毛むくじゃら、いたずら好きな小型の精霊。夜に忍び込んできて悪さをするとされ、寝ているときに噛まれる・息苦しくなるなどの症状を引き起こすと言われています。ベッドの下にレンガを置いて高くして寝るのは、このトコロシュを避けるためだという人も。
アニャンゴ
ナイジェリアなどには、アニャンゴ(Anyango)という死者の霊が女性に取り憑き、奇妙な声で話し出すという民話があり、霊媒やトランス儀式の文脈で登場します。これも「悪霊系」の存在として語られますが、祖霊との橋渡しという側面もあるようです。
シェイプシフター
西アフリカでは人間が動物に変身する話がたくさんあって、特にヒョウ、ハイエナ、ワニに姿を変える「シェイプシフター」がよく登場します。これは“妖怪”というより魔術師や呪術師が持つ力として伝えられていて、変身することで敵を欺いたり、死を免れたりするという意味を持っています。
|
|
|
東アフリカ:山・森・湖にひそむ存在
ポポバワ
ポポバワ(Popobawa)は、ザンジバル(タンザニア)に伝わる、コウモリのような羽を持つ人型の怪物で、夜中に現れ、人々を襲う・悪夢を見せるなどの言い伝えがあります。出現するのは社会的緊張が高まったときと言われていて、政治的・社会的な不安とリンクして語られることも。
ジョガ
ジョガ(Joga)は、ケニアの民話に出てくる、湖や川に住む水の霊で、特定の場所で泳ぐと引きずり込まれると恐れられています。これは日本の「河童」や「海坊主」的な役割に近い存在ともいえますね。
中央・南部アフリカ:呪霊と精霊のはざまで
ムビワ
ムビワ(Mubiwa)は、ジンバブエに伝わる悪霊として知られ、病気や不幸を引き起こす存在です。呪術師(ングァンガ)によって霊を鎮めたり封じ込めたりする儀式が行われます。ムビワは人に乗り移って正気を失わせることもあるとされ、かなり怖がられています。
半人半獣
ナミビアには、動物と人間の中間のような姿の精霊が森や岩場に住んでいて、夜になると人間を試しにやってくるという話があります。自然への畏敬と、神聖な場所に対するタブーを伝える民話としても語り継がれています。
アフリカの“妖怪”は今どう扱われてる?
こうした精霊や怪物の伝承は、口承文化(くちで語り継ぐ文化)の中でずっと残ってきました。学校で教えるものではないけれど、おばあちゃんが夜に話してくれたり、村の儀式で語られたりして、今も子どもたちの心にしっかり根づいています。
最近では、マンガ、映画、アニメーションなどにこうした存在が登場することも増えていて、アフリカの若者文化の中でも妖怪リブート的に生き続けているんです。
アフリカの“妖怪”たちは、ただ怖いだけじゃなく、自然への敬意、社会への教訓、そして人と人の絆を語るメッセンジャー。その土地で生まれた物語には、その土地の生き方がぎっしり詰まっているんですね。
|
|
|