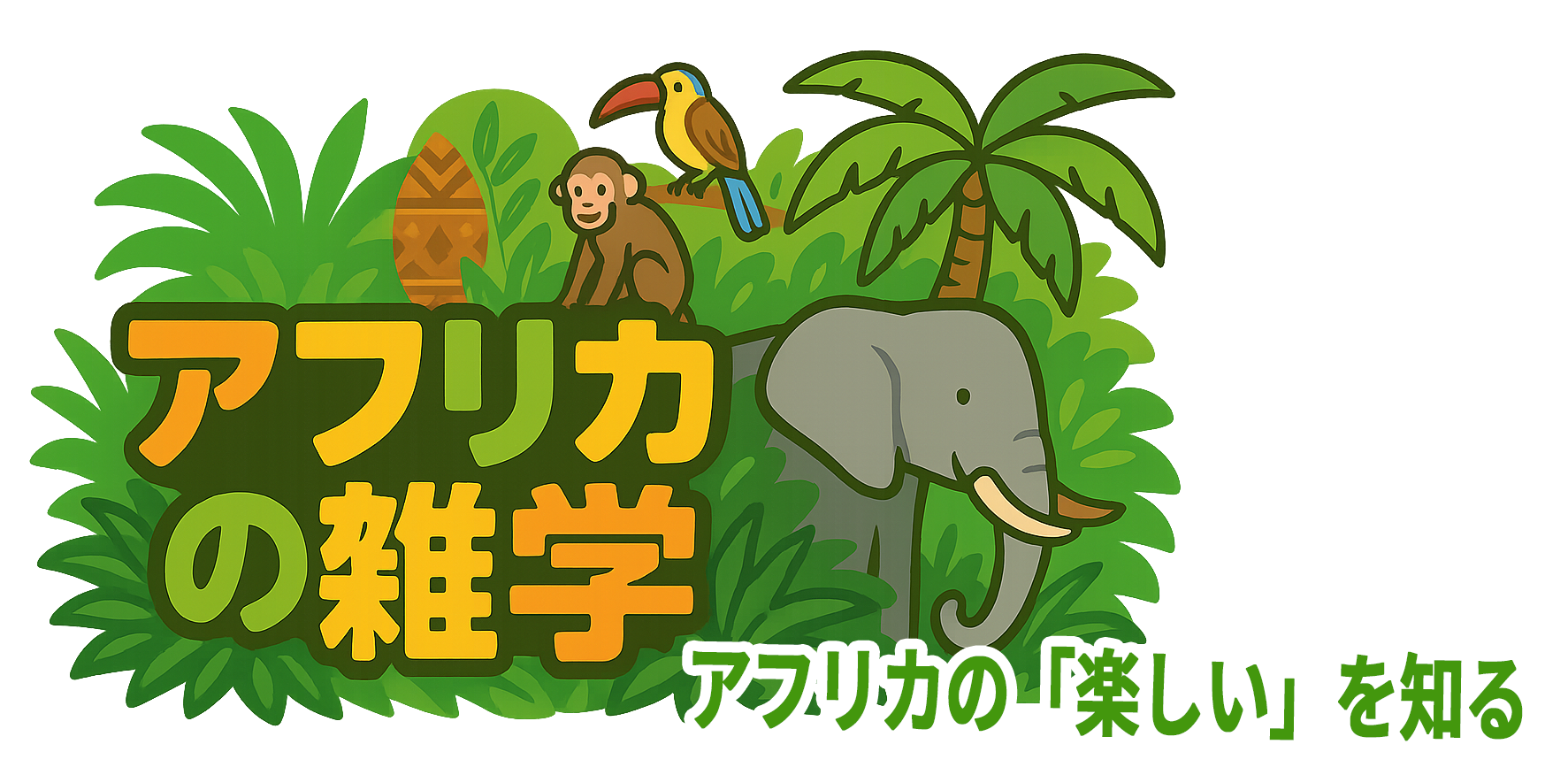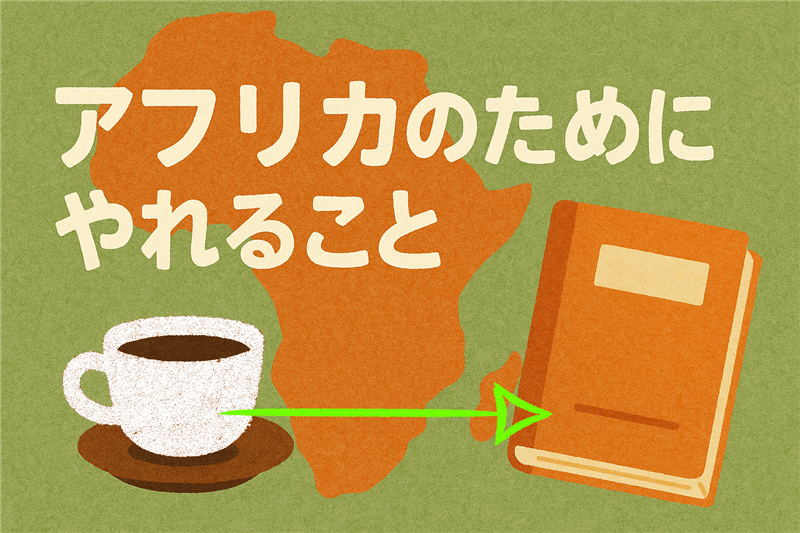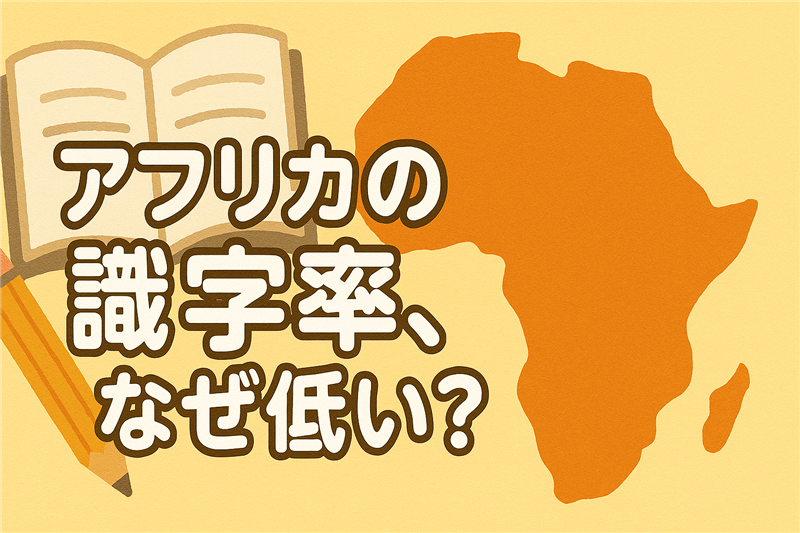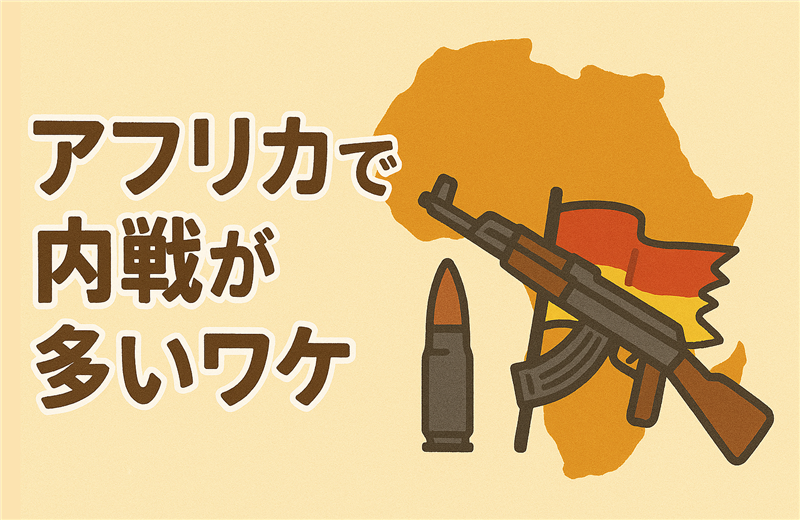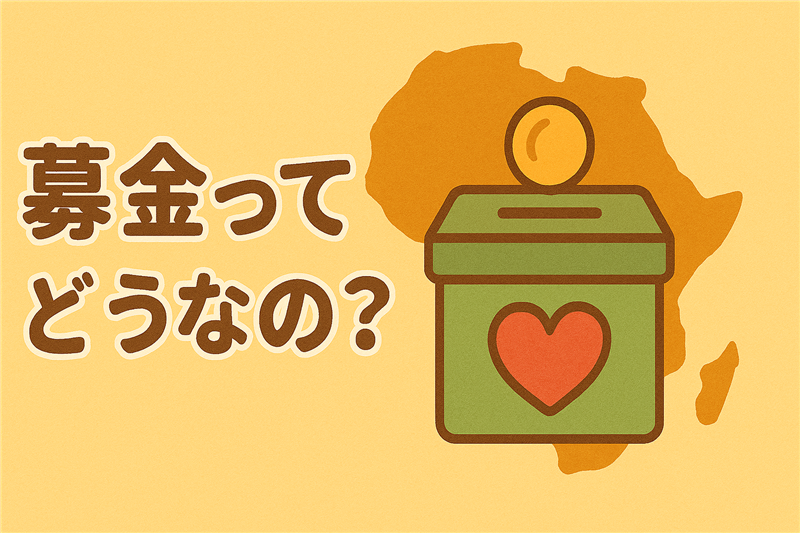アフリカの支援にまつわる雑学5選
「アフリカは支援される側」って思われがちですが、実はその実態はかなり複雑で、驚くような事実もあるんです。ただの“かわいそうな大陸”というイメージでは見えてこない、支援に関するリアルな雑学を5つ紹介します!
|
|
|
1.支援より「搾取」の金額のほうが大きい!?

世界中からアフリカに向かう援助金の合計よりも、アフリカから流出するお金のほうが多いって知ってましたか?
鉱物や石油などの利益が、多国籍企業や税逃れの仕組みで国外に出ていく構造があるため、「援助する」と言いつつ実は“もうけている”国も多いんです。
2.「寄付される服」で服屋さんが潰れる!?

ヨーロッパやアメリカなどから送られてくる古着の大量寄付は、アフリカで販売されることもあります。
でもあまりに安く売られるせいで、地元の衣料品店や仕立て屋さんが経営できなくなるという問題も…。支援のつもりが、現地の経済を壊してしまうこともあるんです。
3.支援のアイコンだった「井戸」が放置されることも

かつて「アフリカ支援=井戸を掘る」が定番のイメージでしたが、掘って終わりの支援だと数年で壊れて使えなくなるケースも多いんです。
最近では、地域の人が自分たちでメンテナンスできるしくみを一緒に作ったり、本当に必要とされている支援かを現地と話し合って決めることが重視されています。
|
|
|
4.一方的な支援ではなく「対等なパートナー」がテーマに

近年の国際協力では、「教えてあげる」「助けてあげる」ではなく、一緒に考えて行動する“共創型”の支援が重視されています。
日本のJICA(国際協力機構)も、専門家を派遣するだけでなく、現地の人材と協力して技術や制度を育てるスタイルにシフトしてきています。
5.「自分たちで作る支援」の動きが広がっている

アフリカの国々では最近、海外からの支援に頼らず、自分たちで問題を解決しようという取り組みが増えています。
たとえばケニアやルワンダでは若者や女性が立ち上げたNPOが、教育支援や環境保護に取り組んでいるんです。
「助けられる側」から「自分たちで立ち上がる側」へという意識の変化が見えてきています。
「支援」って一見いいことのように見えるけど、やり方や考え方しだいで全然ちがう結果になるんです。
アフリカの人たちが本当に必要としているのは、支配でも同情でもなく、対等な協力と信頼関係なのかもしれませんね。
|
|
|